
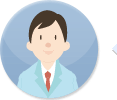
救急診療、外来診療、予防医療の3つの領域から成っています
当科では毎年150件ほどの手術症例を扱っています。最新の内視鏡やカテーテルを用いた
手術にも取り組んでいますが、バイパスやクリッピングなど顕微鏡手術も専門とします。
手術や診療では方針が偏ることなく、患者さんの状態に合わせて常にベストな選択ができる
ように心がけています。
脳神経外科で扱う領域は①救急診療、②外来診療、③予防医療に分類されるため、それぞれについて説明します。
【 ①救急診療 】
外傷と脳卒中に分類されます(24時間対応)。
外傷では整形外科、一般外科など他の診療科とも連係して総合的に対応しています。
緊急手術が必要と判断される重症頭部外傷の場合、頭蓋内圧モニタリング等おこない集中治療室で管理します。
脳卒中では、脳梗塞にはt-PAという強力な血栓溶解剤による治療の他、カテーテルによる血栓除去術、
ステント留置術もおこなっています。脳出血には主に内視鏡で血腫除去術をおこなっています。
くも膜下出血で脳動脈瘤が診断された場合、顕微鏡によるクリッピング術やカテーテルによる
コイル塞栓術をおこないます。
緊急入院した患者さんには、入院当日より早期リハビリテーションを開始します。急性期の治療が終わった段階で
リハビリテーション専門病院へスムーズに転院できるよう手配します。
【 ②外来診療 】
外来では外傷後の経過観察の患者さんは軽快するまで通院します。
脳卒中で退院後の患者さんに対しては、MRI等で定期検査をします。
また、血圧測定、血液検査などから再発予防の指導に努めています。
新規の患者さんは近隣の開業医や院内他科からの紹介が大多数を占めます。
当科で診療後は元の開業医の先生と連携して経過観察することになります。
【 ③予防医療 】
頭痛、めまい、しびれなど症状が心配な方には外来受診を、脳卒中が心配な方、
他科で動脈硬化性疾患を加療している方、成人病や動脈硬化を指摘されている方には脳ドックをお勧めします。
当科で扱う外科的な予防治療としては、未破裂脳動脈瘤に対する開頭クリッピング術、血管内コイル塞栓術、
動脈狭窄病変に対する血行再建術(バイパス)、血管形成術(ステント留置)等があります。
MRAで何らかの異常が示唆された場合、カテーテルによる脳血管撮影をおこないますが、脳血管撮影は
手首の動脈からおこなうため、30分程度で検査後もすぐ歩行可能です。
①②③の枠組みとは別に、脳卒中センターでは、脳卒中の患者さんに対して脳神経内科、脳神経外科、
リハビリテーション科など多職種による総合的なアプローチが可能となるようなチーム編制もしています。
| 久保田 麻紗美 (部長) |
平成25年 日本医科大学卒
日本脳神経外科学会専門医 |
| 藤田 寛明 |
令和3年 日本医科大学卒
|
| 立澤 孝幸 | 昭和55年 日本医科大学卒 医学博士 日本脳神経外科学会専門医 日本医師会認定産業医 |
| 鮫島 哲朗 | 浜松医科大学 脳神経外科 講師 (平成2年 宮崎医科大学卒業) 平成14~18年 Duke University Medical Center, Neurosurgery 日本脳神経外科学会認定専門医、日本脳卒中学会認定専門医 (専門) 頭蓋底手術(聴神経や下垂体部腫瘍、髄膜腫、顔面痙攣、三叉神経痛) |